銅の発色技術とは

私たちの日常生活はさまざまな色に囲まれていると思います。
自然界の色を感じることもありますが、身の回りのモノを見るとその多くが人工的なものです。
その人工的な色から連想されるのは、染料のような着色させるためのものをあてがうことではないでしょうか。
衣類であれば染料、建物であればペンキなど色のついたものと融合させることで「黄色の服」のような状態を作り上げています。
ところがその先入観だけでは語れないモノがあります。
それが銅器ををはじめとする金属の発色を利用したものです。
銅製品でまずイメージできるのは銅メダルでもお馴染みの茶褐色のような色です。
そんな代表的な色をはじめとし、さまざまな色の銅製品が存在するのです。
歴史が裏付ける新潟の技術

さまざまな色に発色させることは伝統の技術としてその地域に根付いていいます。
もしそれが大量生産されている染料によるものであったなら、きっとそれらの商品はもっと身近で私たちの生活にも当たり前のように存在していたのかもしれません。
しかし現実には一つ一つにが職人の技術によって美しい姿に作り上げられたものなのです。
色の種類には以下のようなものがあります。
普段あまり目にすることができない技術はどんな地域で伝承されているものでしょうか。
その一つとして有名なのが新潟県です。
もともとは信濃川の氾濫から農民を救うために派遣された鍛冶職人たちの影響で、燕三条には金属の加工文化があったといわれます。
そして1650年ごろから銅細工の製作が行われるようになりますが、その後1700年ごろには燕市の北に位置する弥彦山から銅が算出され銅製品の生産も盛んになりました。
銅製品のある生活

色を「着ける」のではなく「生みだす」という手法で作られる銅製品の数々。
近代的な文明が主役になり都市圏に目が向きがちな昨今だからこそ、改めて日本古来の魅力に着目してみるのはとても有意義なことではないでしょうか。
世界での日本の競争力も悲観的に見られることが多いですが、まだまだ日本には世界に誇れるメイドインジャパンを隠し持っていると私たちは確信しています。
その忘れられがちな日本の魅力に、まずは日本人が気づいてみるというは決して無駄なことではないでしょうか。
LAFUGOでは日本の誇る技術力が詰め込まれた工芸品に関する口コミを多く取り扱っております。この機会に是非チェックしてみてください。
↓↓ 工芸品が気になった方は是非一度口コミを見てみてください。 ↓↓


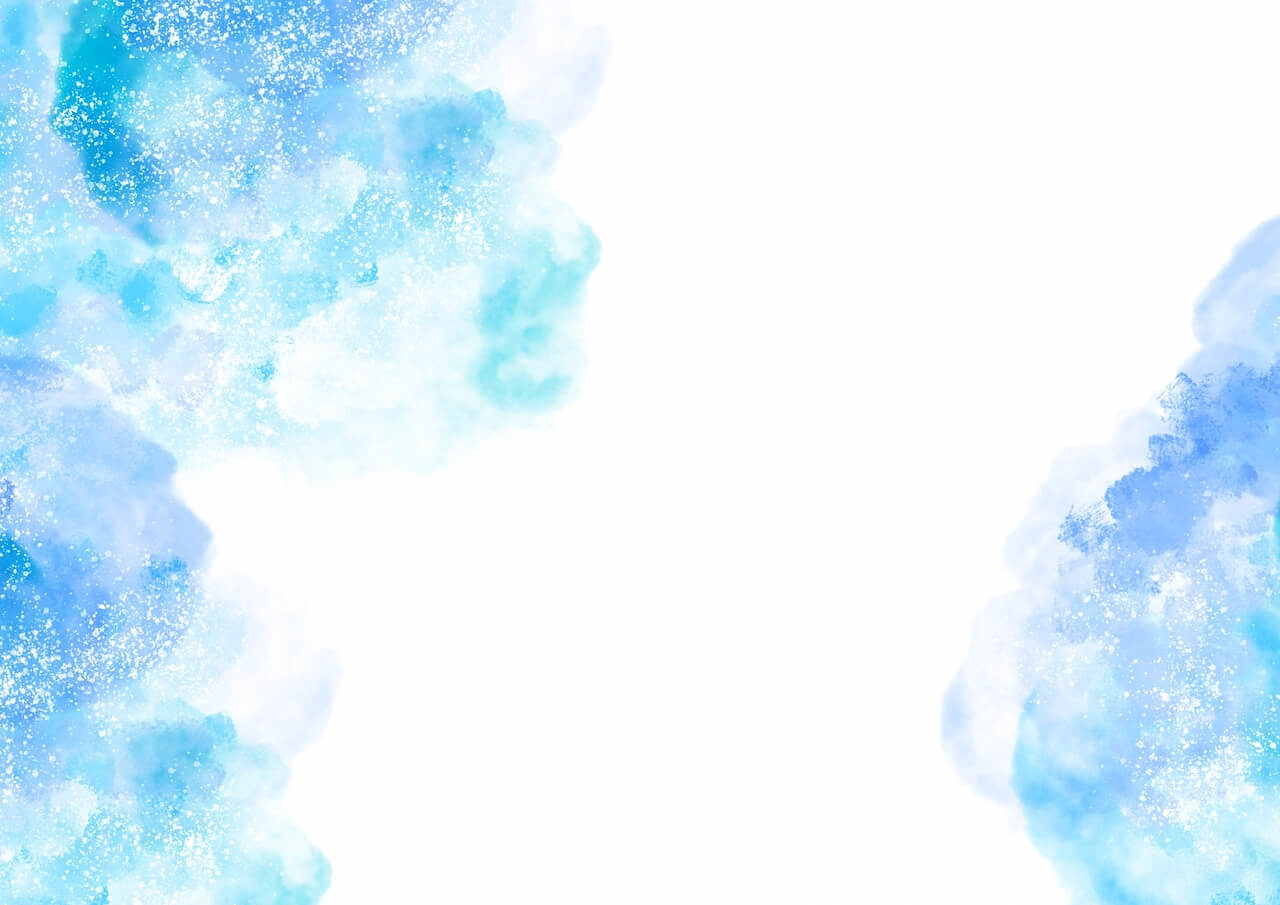


コメント